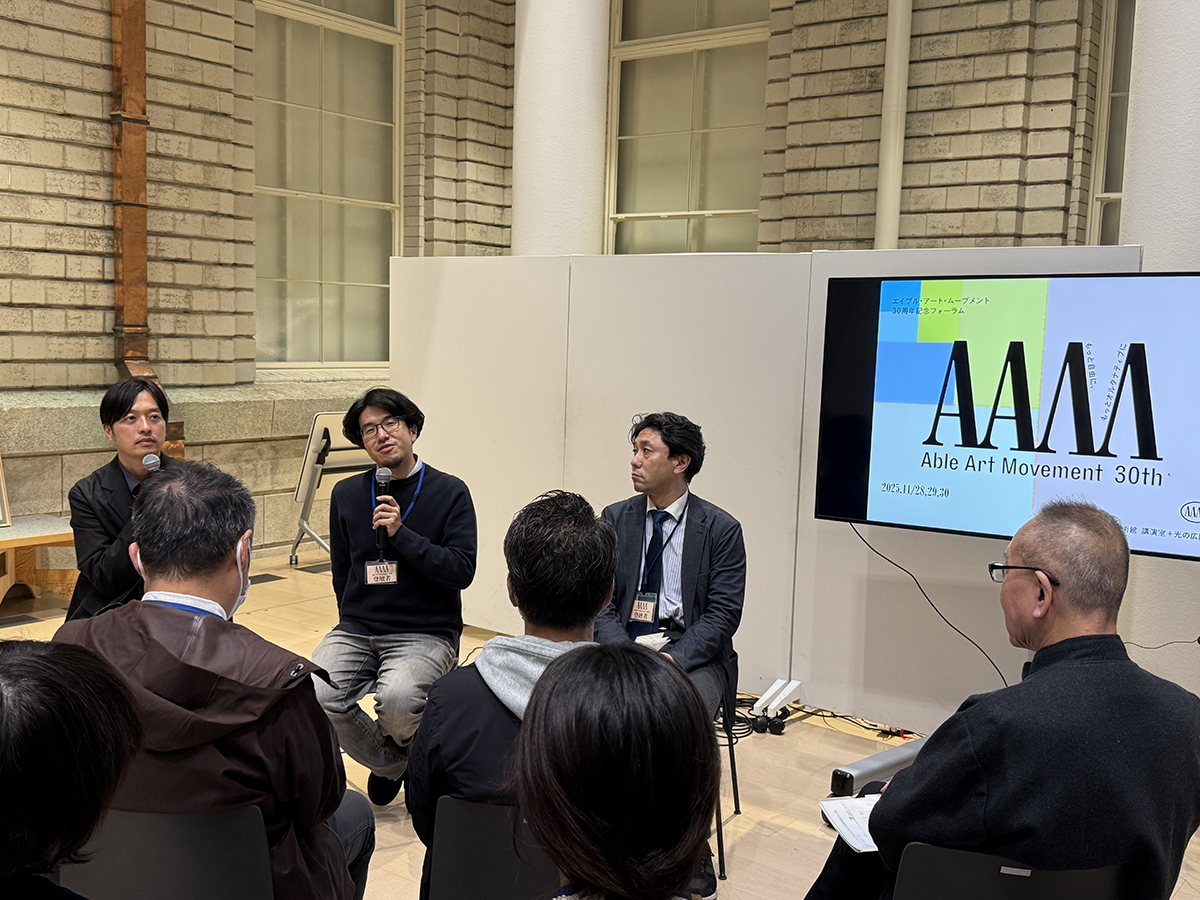京都国立博物館で「仏法東漸」 1500年前の最古の写経や空海の「直筆メモ」も

京都国立博物館(京都市東山区)で7月29日、「仏法東漸 仏教の典籍と美術」が始まった。京都の16の仏教に縁のある大学でつくる京都仏教各宗学校連合会との共催。
展示では「釈尊の教え」「教えのひろがり」をテーマに2部で展開。仏教各宗派の宗祖に焦点を当て、それぞれの宗祖に関連する書跡や絵画、工芸品を展示する。「大蔵会(だいぞうえ)」100回を記念して同館で行う。「大蔵会」とは、仏教に関する典籍の展覧を中心とした仏教行事。大正天皇の即位に合わせて1914(大正3)年に行われたのが最初。現在は、京都のみで続けられている。
第1部では、現存する経典の中で最も古く、およそ1500年前のものといわれている「菩薩処胎経(ぼさつしょたいきょう)」の第3巻を展示。同経典は、釈迦の入涅槃(にゅうねはん)の前後を題材とし母体内で説法するという内容で、現存する写経としては最古のもの。知恩院第七十五代鵜養徹定 (うがいてつじょう)の蒐集(しゅうしゅう)品で、清末の外交官は、日本にこれほど古い写経が伝播(でんぱ)していたことに驚嘆したという。
第2部では、空海筆の「灌頂歴名(かんじょうれきめい)」1巻を展示。同歴名は、空海が高雄山寺(のちの神護寺)で、「灌頂」を授けた人物の名前を記録したもの。筆頭に天台宗の開祖の最澄(さいちょう)の名前があることから、両者の交流を知ることのできる資料として国宝に指定されている。
連合会代表で大谷大学の宮崎健司教授は「各宗派の総本山と同連合会の協力の下、これだけのものが一堂に会することができた。なかなかない機会なので、ぜひ来てほしい」と来館を呼び掛ける。
開催時間は9時30分~17時。入館料は、一般=520円、大学生=260円、高校生以下と満18歳未満・満70歳以上は無料。9月6日まで。